結論
収め方のパターンを覚える。
普通はこうなるでしょ(建築の常識)を身につける。
問題点を整理して取捨選択をする。
エスキスがまとまらない原因って?
課題を解いていく中で大半の人が当たる壁、エスキスまとまりません。
何がどうまとまらないの?⇨分かりません、どうしたらいいんですか。⇨解答を見て「あー」
この繰り返しで自身の成長が感じられない、学科では点数として成長を感じることができそれがモチベーションにもなっていたと思います。
エスキスまとまらない⇨課題が解けない⇨苦しい、いやだ⇨宿題終わらない⇨どうすれば・・・
負のスパイラルにより自身の自尊心がボコボコにされ「センスがない」「向いてない」で結論付けようする人もいますが心配しないでください。
資格学校で出てくる課題は問題の対処方法を教えるための課題です。
知らない問題を解いて出来る人が少ないんです、過年度生は知ってるから解ける、それだけの話なんです。
だから自信をなくしたり、卑下したりする必要は全くありません。
解けなくて当たり前、解けない課題を解く道中で知識を身につけるための課題なんです。
何を身につければエスキスができるようになるの?
人によって様々なので一概には言えないですが、結論にも書いたように複数の解決方法があります。
収め方のパターンを覚える
収まりを覚えるために「パーツトレーニング」をします。
パーツトレーニングはエスキスノートにフリーハンドでパーツ(階段・便所・玄関・部屋)を描くことです。
ちなみに5mm方眼紙は100均にあります、通常のエスキスノートよりお得なのでオススメです。
4.55mmは流石にないのでエスキスノートを使用しましょう。
パーツはよく使うものならなんでもいいです、課題の解答例から抜き出したりしましょう。
一級ならコアパーツを1セット、二級なら水回り(便所・脱衣室・浴室)ですね。
なぜこの方法でエスキスが上達するのか。
それはエスキス段階で細かい寸法・収まりまでイメージができるからです。
これが出来ると出来ないではエスキスのまとめ方に雲泥の差があります。
結局設計製図のエスキスって大枠(箱をイメージ)を作ってその中に動線を考慮して間仕切りしていくだけなんです。(それが出来ないから苦労するんですが)
その間仕切りをしていく中で最小の組み合わせを持っている人と持ってない人じゃ差ができて当然です。
建築の常識を身につける
意匠設計を生業にしている方や普段から設計している人と普段は別の仕事をしている人だと問題文に書かれている要求事項の受け取り方が違うことが多々あります。
この認識の差により出来上がったプランが全然違ってきます。
講師をしているのですが教える際にどう教えたらいいかよく迷います。
内心「なんでこうなった・・・」「これはないな、流石に」と思うこともありますがそれをそのまま伝えるわけにはいきません。
普通が分からないからそうなっている、ワザとやっているわけではなく本人は至って真剣です。
対処法としては身の回りの建築物を観察することです。
現在周りにある建築物は全てプロの解答です、もちろん良い物もあれば悪い物もあります。
自分ならこうするのに
なんでこうなった?理由があるのか?
こういうプランにしたのか、なるほど
と建築に対する観察眼を養いましょう。
コロナ禍で見学なんかできないよ、そんな時間ないし
いやいや、自分の住んでいる建物はどうですか?
資格学校に行ってる方は学校内や買い物とか行きませんか?
会社はどうですか?昼ごはん食べに行ったりしますか?
自分が思っている以上に周囲には建築物があり、それを利用している人がいますよ。
問題点を整理して取捨選択する
また続き書きます。
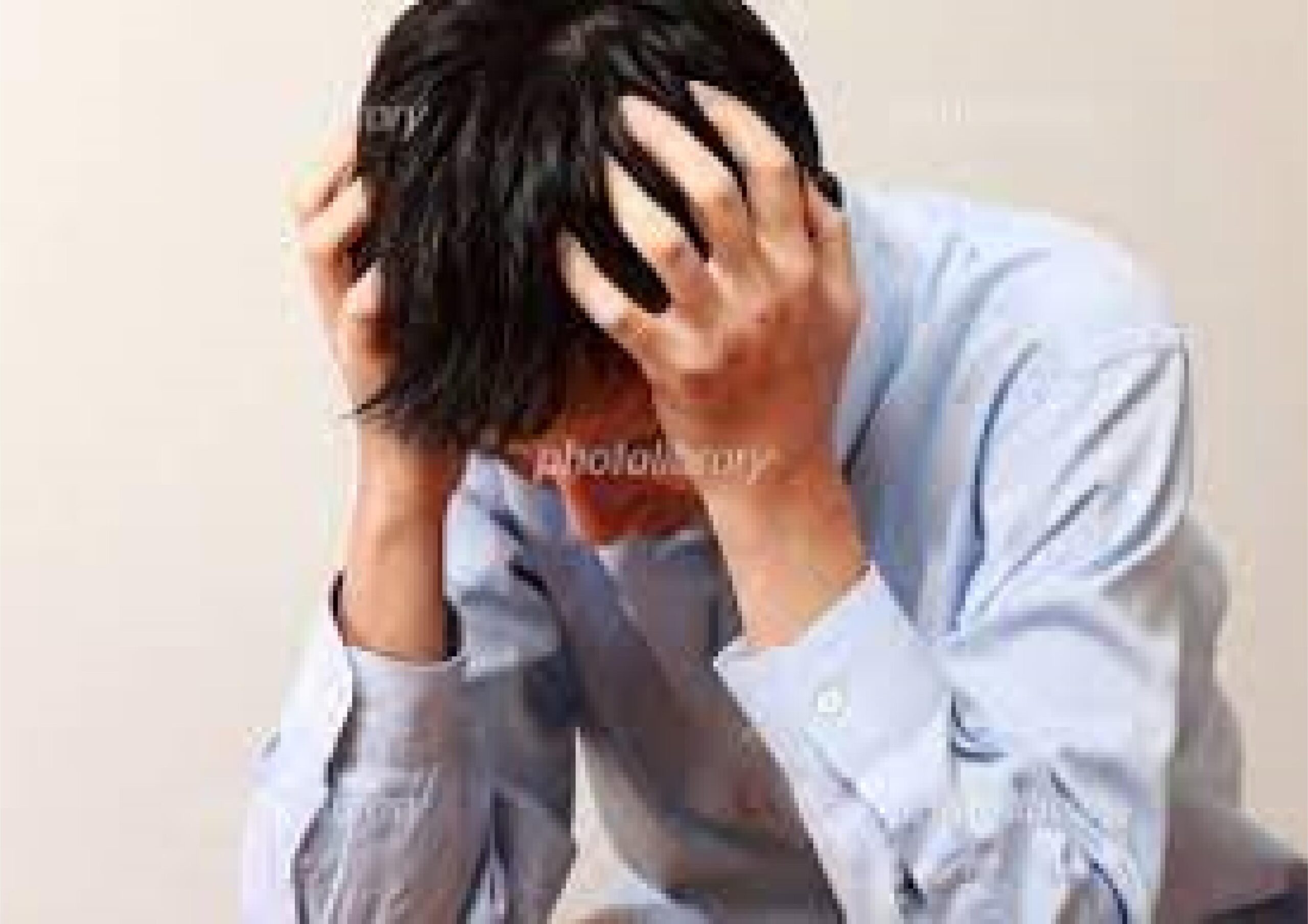


コメント